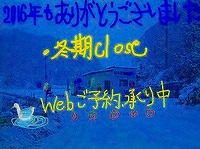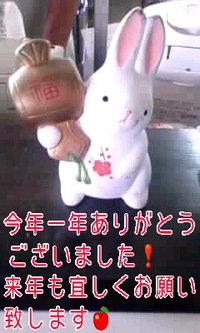2012年09月06日
収穫
皆様こんにちわ。松木武久農園の営業担当です。
本日は、慣行栽培の畑の作業風景です。
~当農園は、父:武久君が、祖父より受け継いだ畑を、18歳から、りんご栽培一筋で、りんご専業農家としてやってまいりました。現状では、99%が、慣行栽培での栽培となっております。~
*当時の長野市は、まだ、りんご栽培の創世記で、青森のりんご農家さんの元に弟子入りさせて頂き、大変にお世話になり、苗木もたくさん分けて貰ったらしいです(武久談)
~残りの1%は、自然栽培:無農薬・無化学肥料・草も刈らない。害虫駆除の為に、酢の希釈液を散布。~
9年ほど前より、営業担当兼、後継ぎのわたくしが、
「後を継ぐなら、どーーーーしても、無農薬栽培に挑みたい!!
店舗のお客様や、わたしの友人達が、入院中のおじいさんの為や、妊娠のつわりの時期、離乳食にりんごや、ジュースを購入してくれる・・・りんごジュースには、一切添加物も防腐剤も入れてないけど・・・りんごの木に、両親が真っ白になって帰ってくる程、農薬をかけてる・・・
大切なお客様や、友人達の孫子の代まで、うちのりんごを食べて安全だ!・・・と胸を張って言えるのか?
どーすれば? 野菜は、お米の無農薬は出来るらしいが・・・」
と・・・調べまくって、木村秋則氏に辿り着き、一本だけ、りんごの木を貰いうけ、無農薬栽培に取り組んでおります。
(こちらのブログのカテゴリー:自然栽培、畑で考えたコトの過去記事をご覧下さいませ。)
*今年から、自然栽培の畑を増やしておりますが、一年目で、様子見段階でございます。
注:販売に至るには、まだまだ年数がかかるかと・・・思われます。
松木武久農園の慣行栽培法
・店舗開店の年より、除草剤は、一切まかない(経費削減と、武久君の方針により)
・草は刈り、夏の日差しで焼けてしまう、木の根元に撒きます。(主に、うさぎと、母の仕事:祖父が生きてる頃は、祖父。)
*ちなみに、「自然栽培」では、草は一切刈りません!! ⇔嘘でした!!忘れてました。木村式自然栽培でも、秋場には草を刈るのですが、私は刈ったり、刈らなかったり・・・で、すっかり忘れてました!!
コメント欄:B4さん指摘
「木村さんの方法では、9月に入るとりんごに季節を感じさせる為に(熟させる)、下草を刈ると本で書いていました。
園の気温を下げる為です。」
・農薬は、JA・県農政課の指導による 「防除暦」(散布する農薬の種類、時期を暦にした物)を元に、通常は、年12~13回散布のところを、7~8回に抑えて、散布。
平成23年りんご病害虫防除暦(五所川原JA )・・・http://www.ja-goshotsugaru.com/boujyoreki-23.htm
防除暦は年末に、各地方の主要産地ごとに農協や農業技術者が、前年度の防除成績と 次年度の病害虫の発生予想・農薬の効果や薬害発生状況の反省の下、毎年新しく編成 されます。それに基づき、翌年の農薬や防除機具の調達が前以って行われます。・・・http://www.medianetjapan.com/2/20/government/jangshogun/Disease7.htm

9月5
午後から、塔の尾の畑で草チラシ。下の畑(主に、品種は、秋映)だけおわして、畑を移動。
シャリの畑で、消毒作業前に、早生品種を収穫(スーパー卸し・贈答用)
~塔の尾の畑~





*サンふじは、まだ青々してます。ここから、2ヶ月以上かけて、実も大きくなり、色が付き、デンプン質が糖度に変わっていきます。どんな品種にも、収穫の旬があります。
*相場の価格変動に左右されて、りんごの木や、りんごの実の都合ではなく、人間の都合だけで収穫を早めると・・・・
美味しい筈の品種も、本来の旬ではない時期に、市場に流通してしまうと、本来の味わいを堪能できません。
(たった一日違っても味わいは変わります。
例えば:今日、初めて、「あんよ」・・・が出来たから、昨日も立てる?・・とは限らず、赤ん坊には、赤ん坊の「あんよ」出来る日がやってくるもの。)
しかし、特に新しい品種を初めて購入して味わったお客様にとっては、
「たった一つだけ食べた、りんごが、その品種のイメージとして固定化されてしまいがち。」
(シナノゴールドなどは、収穫時季を早め過ぎて、「美味しくない!」というイメージが消費者についてしまう危惧があり、県の農政課から、各農家にPRのポスターが配布されたりしておりました。)
*農家にとっては、農産物は生活の糧であり、
~市場に出回らない、一番真っ先に出荷すると、比較的、高価格で値がつく~
当然、一年間、手塩にかけて、経費もかけて、育てたのだから、少しでも高く売りたい!!
という事情があります。 それがイヤ
(経理担当の母が、相場事情から、りんごの完熟前に収穫しようと言うと、畑担当の父が絶対に収穫させない!!)
で、考えあぐねた母が、直売所を開店した訳です。自社店舗があり、価格も自分で決められて、お客様に直接、販売できれば、市場価格に左右されずに、
「りんごを完熟前に収穫するなんて、絶対にしない!!」
父の筋も通せる・・・むしろ、それがお客様にも喜ばれる。
~伺里の畑、遠景~





*明日、晴れなら、この畑も消毒に入るので、急遽、収穫に入ったので、はしご持参して来なくて・・・木に登り収穫しました。
 結局、本日は雨で、消毒作業は3日後くらい先延ばしましたが、作業前倒しできて、冷蔵庫に収穫した、りんごちゃんを保存できたので(早生品種、早く収穫できる品種ほど、日持ちがしません。一番、日持ち・保存がきく品種は、サンふじ!)、良しとする。
結局、本日は雨で、消毒作業は3日後くらい先延ばしましたが、作業前倒しできて、冷蔵庫に収穫した、りんごちゃんを保存できたので(早生品種、早く収穫できる品種ほど、日持ちがしません。一番、日持ち・保存がきく品種は、サンふじ!)、良しとする。
本日は、慣行栽培の畑の作業風景です。
~当農園は、父:武久君が、祖父より受け継いだ畑を、18歳から、りんご栽培一筋で、りんご専業農家としてやってまいりました。現状では、99%が、慣行栽培での栽培となっております。~
*当時の長野市は、まだ、りんご栽培の創世記で、青森のりんご農家さんの元に弟子入りさせて頂き、大変にお世話になり、苗木もたくさん分けて貰ったらしいです(武久談)
~残りの1%は、自然栽培:無農薬・無化学肥料・草も刈らない。害虫駆除の為に、酢の希釈液を散布。~
9年ほど前より、営業担当兼、後継ぎのわたくしが、
「後を継ぐなら、どーーーーしても、無農薬栽培に挑みたい!!
店舗のお客様や、わたしの友人達が、入院中のおじいさんの為や、妊娠のつわりの時期、離乳食にりんごや、ジュースを購入してくれる・・・りんごジュースには、一切添加物も防腐剤も入れてないけど・・・りんごの木に、両親が真っ白になって帰ってくる程、農薬をかけてる・・・
大切なお客様や、友人達の孫子の代まで、うちのりんごを食べて安全だ!・・・と胸を張って言えるのか?
どーすれば? 野菜は、お米の無農薬は出来るらしいが・・・」
と・・・調べまくって、木村秋則氏に辿り着き、一本だけ、りんごの木を貰いうけ、無農薬栽培に取り組んでおります。
(こちらのブログのカテゴリー:自然栽培、畑で考えたコトの過去記事をご覧下さいませ。)
*今年から、自然栽培の畑を増やしておりますが、一年目で、様子見段階でございます。
注:販売に至るには、まだまだ年数がかかるかと・・・思われます。
松木武久農園の慣行栽培法
・店舗開店の年より、除草剤は、一切まかない(経費削減と、武久君の方針により)
・草は刈り、夏の日差しで焼けてしまう、木の根元に撒きます。(主に、うさぎと、母の仕事:祖父が生きてる頃は、祖父。)
*ちなみに、「自然栽培」では、草は一切刈りません!! ⇔嘘でした!!忘れてました。木村式自然栽培でも、秋場には草を刈るのですが、私は刈ったり、刈らなかったり・・・で、すっかり忘れてました!!
コメント欄:B4さん指摘
「木村さんの方法では、9月に入るとりんごに季節を感じさせる為に(熟させる)、下草を刈ると本で書いていました。
園の気温を下げる為です。」
・農薬は、JA・県農政課の指導による 「防除暦」(散布する農薬の種類、時期を暦にした物)を元に、通常は、年12~13回散布のところを、7~8回に抑えて、散布。
平成23年りんご病害虫防除暦(五所川原JA )・・・http://www.ja-goshotsugaru.com/boujyoreki-23.htm
防除暦は年末に、各地方の主要産地ごとに農協や農業技術者が、前年度の防除成績と 次年度の病害虫の発生予想・農薬の効果や薬害発生状況の反省の下、毎年新しく編成 されます。それに基づき、翌年の農薬や防除機具の調達が前以って行われます。・・・http://www.medianetjapan.com/2/20/government/jangshogun/Disease7.htm
9月5

午後から、塔の尾の畑で草チラシ。下の畑(主に、品種は、秋映)だけおわして、畑を移動。
シャリの畑で、消毒作業前に、早生品種を収穫(スーパー卸し・贈答用)
~塔の尾の畑~
*サンふじは、まだ青々してます。ここから、2ヶ月以上かけて、実も大きくなり、色が付き、デンプン質が糖度に変わっていきます。どんな品種にも、収穫の旬があります。
*相場の価格変動に左右されて、りんごの木や、りんごの実の都合ではなく、人間の都合だけで収穫を早めると・・・・
美味しい筈の品種も、本来の旬ではない時期に、市場に流通してしまうと、本来の味わいを堪能できません。
(たった一日違っても味わいは変わります。
例えば:今日、初めて、「あんよ」・・・が出来たから、昨日も立てる?・・とは限らず、赤ん坊には、赤ん坊の「あんよ」出来る日がやってくるもの。)
しかし、特に新しい品種を初めて購入して味わったお客様にとっては、
「たった一つだけ食べた、りんごが、その品種のイメージとして固定化されてしまいがち。」
(シナノゴールドなどは、収穫時季を早め過ぎて、「美味しくない!」というイメージが消費者についてしまう危惧があり、県の農政課から、各農家にPRのポスターが配布されたりしておりました。)
*農家にとっては、農産物は生活の糧であり、
~市場に出回らない、一番真っ先に出荷すると、比較的、高価格で値がつく~
当然、一年間、手塩にかけて、経費もかけて、育てたのだから、少しでも高く売りたい!!
という事情があります。 それがイヤ
(経理担当の母が、相場事情から、りんごの完熟前に収穫しようと言うと、畑担当の父が絶対に収穫させない!!)
で、考えあぐねた母が、直売所を開店した訳です。自社店舗があり、価格も自分で決められて、お客様に直接、販売できれば、市場価格に左右されずに、
「りんごを完熟前に収穫するなんて、絶対にしない!!」
父の筋も通せる・・・むしろ、それがお客様にも喜ばれる。
~伺里の畑、遠景~
*明日、晴れなら、この畑も消毒に入るので、急遽、収穫に入ったので、はしご持参して来なくて・・・木に登り収穫しました。
 結局、本日は雨で、消毒作業は3日後くらい先延ばしましたが、作業前倒しできて、冷蔵庫に収穫した、りんごちゃんを保存できたので(早生品種、早く収穫できる品種ほど、日持ちがしません。一番、日持ち・保存がきく品種は、サンふじ!)、良しとする。
結局、本日は雨で、消毒作業は3日後くらい先延ばしましたが、作業前倒しできて、冷蔵庫に収穫した、りんごちゃんを保存できたので(早生品種、早く収穫できる品種ほど、日持ちがしません。一番、日持ち・保存がきく品種は、サンふじ!)、良しとする。Posted by 松木うさぎ at 12:17│Comments(1)
│松木武久農園について
この記事へのコメント
http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nougi/newninsyo/ninsyohome2.htm
長野県の農産物認証制度は、2013年から、30%減 → 50%削減に基準が改定されました。
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf#search='農薬カウント'
減農薬・減化学肥料の表示も禁止なのですね。
JAS有機栽培法で、農薬としてカウントされない自然由来の物質(化学合成しない)に、石灰硫黄合剤、硫酸銅(ボルドー)、生物農薬(BT剤など)があります。
ダニ剤のコロマイト(ミルベクチン)もそうです。
散布回数のみならず、使用農薬カウントも考慮すればよいと思います。
(信濃町の 落影農産物生産者組合では、とうもろこしにBT剤使用で減農薬です。)
慣行栽培での農薬使用だと、散布回数を削減しても7-8回または9回が限度でしょう。(3月末のマシン油、石灰硫黄合剤を含めて)
今年のように少雨ですと病気、害虫の発生は比較的おとなしいです。
桃やプルーンなどの散布も定期に行われますので、りんごへのシンクイ虫被害も軽微。
私は昨年からICボルドー使用に切り替え、昨年今年とも合計で6回・・・これ以下にはできません。
8月末に止め消毒で3度めのボルドー使用してです。
(ダニ発生被害の大きい園は8月末と9月中旬=止め消毒・・・を通常農薬にしました。)
過去2年は降れば大雨、今年は高温乾燥で、どちらにしても気が休まることはありません。
防除暦通りの2週間おき散布ならば、枕を高くして寝れますが・・・。
反面、コストは恐ろしく嵩み、散布回数の頻度も多いからシンドイ。
しかし、薬剤数に於いては、防除暦の半分以下になります。
殺菌剤の複数使用が必要ありません。
今年の長い夏と猛暑によりアップルラインではナミハダニ発生があり、カネマイト、ダニサラバ(スターマイト)とダニゲッター使用となりました。
ボルドーの弱点はダニと豪雨です。
当地よりも標高が高い浅川斜面ですので、ダニ警戒は低くて済みそうですね。
木村さんの方法では、9月に入るとりんごに季節を感じさせる為に(熟させる)、下草を刈ると本で書いていました。
園の気温を下げる為です。
私は認証を取る意志は今のところありませんが、減農薬に関してははっきり自信もって自分が栽培収穫したりんごをお客さんに薦められます。
もう、ICボルドー体系から防除暦の一般農薬には戻れません、戻る気もありません。
自分が口にしたくないものを、人様に食べさせられないからです。
ほぼ”葉とらず仕様”での味のキレ、そしてふじは”普通ふじの食味”が着系とは比べ物にならない美味だからです。
ふじに関しては、普通ふじ(栽培しにくい)と減農薬の2重苦を背負って格闘中です。
長野県の農産物認証制度は、2013年から、30%減 → 50%削減に基準が改定されました。
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf#search='農薬カウント'
減農薬・減化学肥料の表示も禁止なのですね。
JAS有機栽培法で、農薬としてカウントされない自然由来の物質(化学合成しない)に、石灰硫黄合剤、硫酸銅(ボルドー)、生物農薬(BT剤など)があります。
ダニ剤のコロマイト(ミルベクチン)もそうです。
散布回数のみならず、使用農薬カウントも考慮すればよいと思います。
(信濃町の 落影農産物生産者組合では、とうもろこしにBT剤使用で減農薬です。)
慣行栽培での農薬使用だと、散布回数を削減しても7-8回または9回が限度でしょう。(3月末のマシン油、石灰硫黄合剤を含めて)
今年のように少雨ですと病気、害虫の発生は比較的おとなしいです。
桃やプルーンなどの散布も定期に行われますので、りんごへのシンクイ虫被害も軽微。
私は昨年からICボルドー使用に切り替え、昨年今年とも合計で6回・・・これ以下にはできません。
8月末に止め消毒で3度めのボルドー使用してです。
(ダニ発生被害の大きい園は8月末と9月中旬=止め消毒・・・を通常農薬にしました。)
過去2年は降れば大雨、今年は高温乾燥で、どちらにしても気が休まることはありません。
防除暦通りの2週間おき散布ならば、枕を高くして寝れますが・・・。
反面、コストは恐ろしく嵩み、散布回数の頻度も多いからシンドイ。
しかし、薬剤数に於いては、防除暦の半分以下になります。
殺菌剤の複数使用が必要ありません。
今年の長い夏と猛暑によりアップルラインではナミハダニ発生があり、カネマイト、ダニサラバ(スターマイト)とダニゲッター使用となりました。
ボルドーの弱点はダニと豪雨です。
当地よりも標高が高い浅川斜面ですので、ダニ警戒は低くて済みそうですね。
木村さんの方法では、9月に入るとりんごに季節を感じさせる為に(熟させる)、下草を刈ると本で書いていました。
園の気温を下げる為です。
私は認証を取る意志は今のところありませんが、減農薬に関してははっきり自信もって自分が栽培収穫したりんごをお客さんに薦められます。
もう、ICボルドー体系から防除暦の一般農薬には戻れません、戻る気もありません。
自分が口にしたくないものを、人様に食べさせられないからです。
ほぼ”葉とらず仕様”での味のキレ、そしてふじは”普通ふじの食味”が着系とは比べ物にならない美味だからです。
ふじに関しては、普通ふじ(栽培しにくい)と減農薬の2重苦を背負って格闘中です。
Posted by B4 at 2012年09月16日 15:32